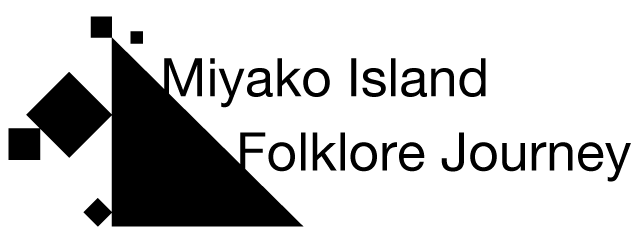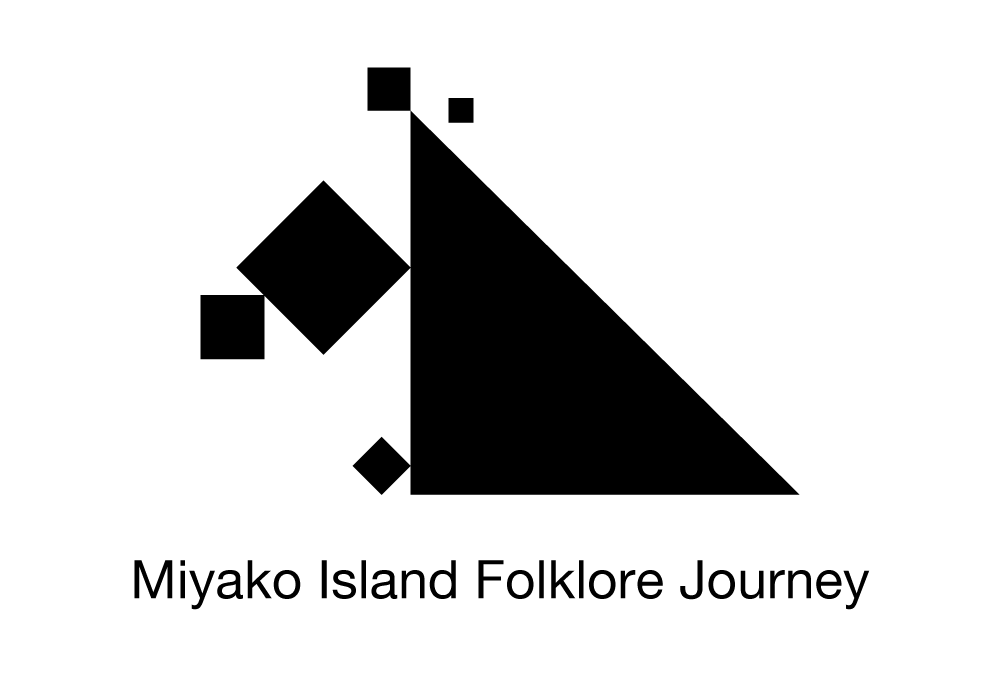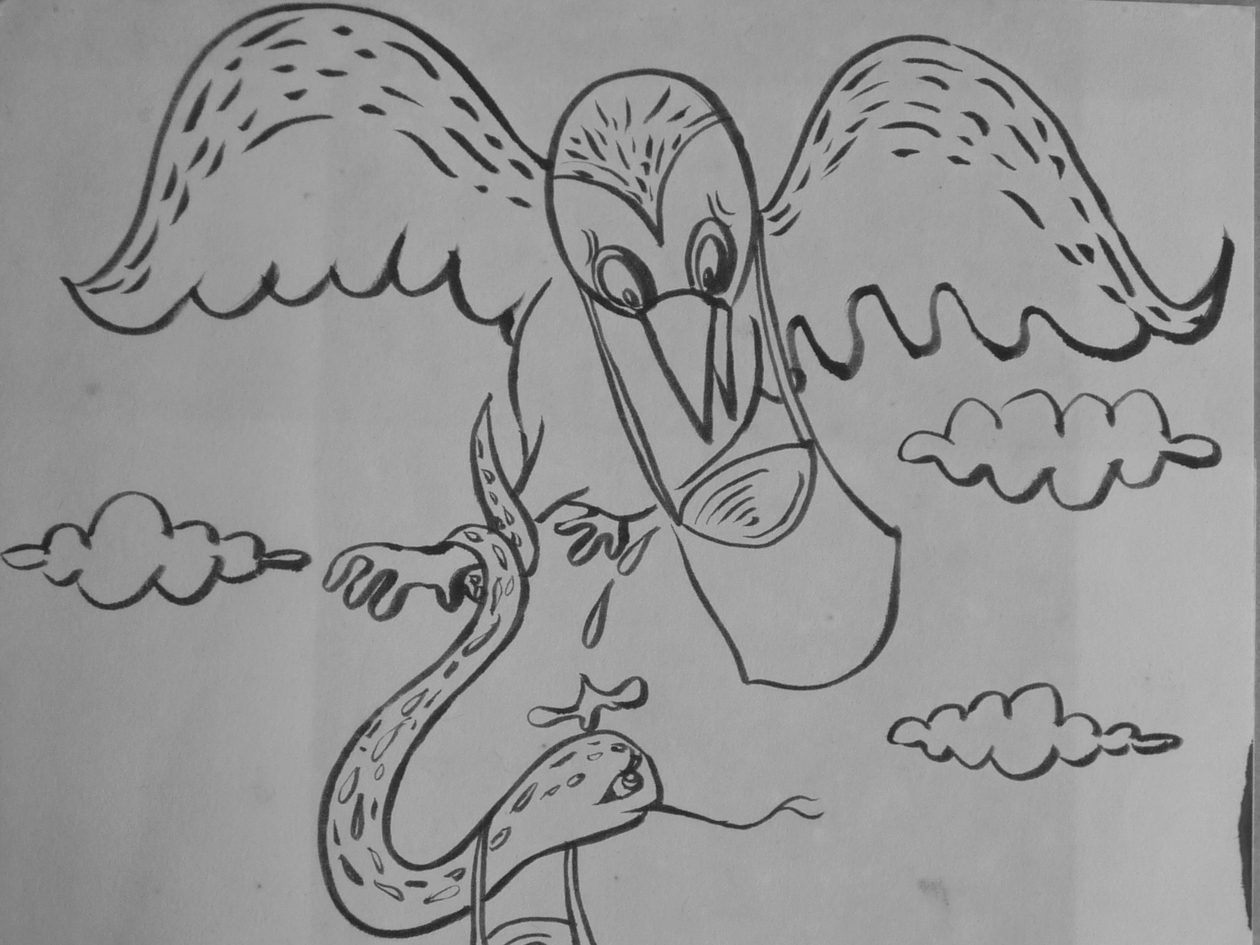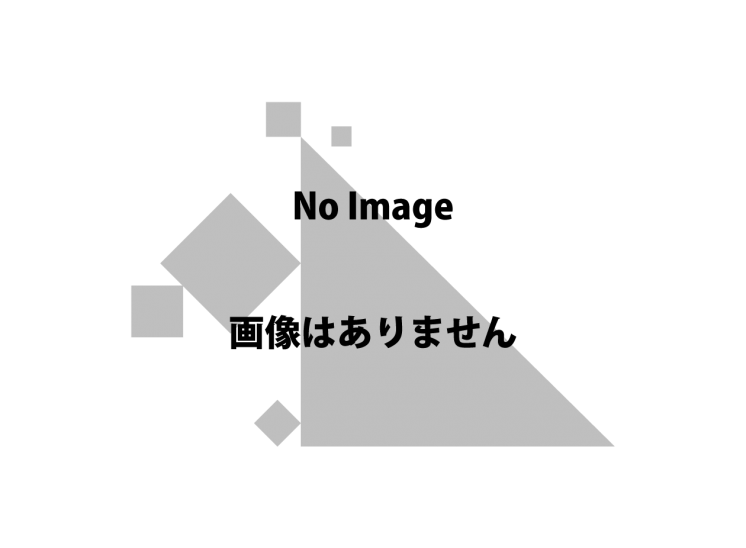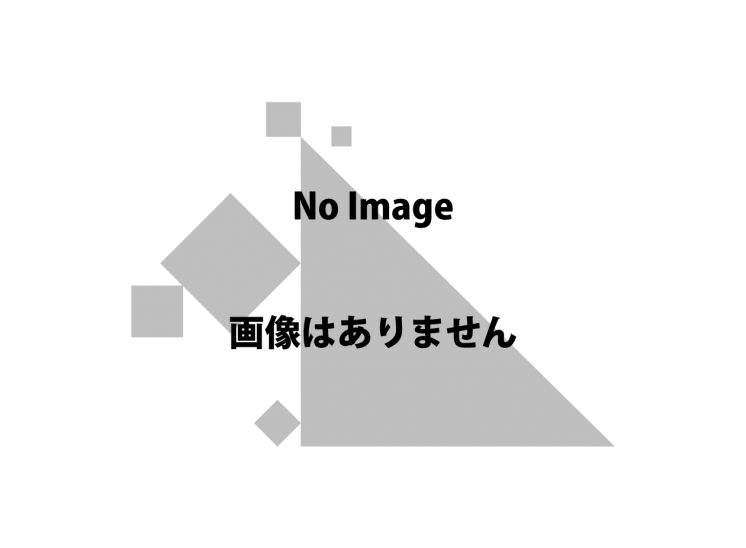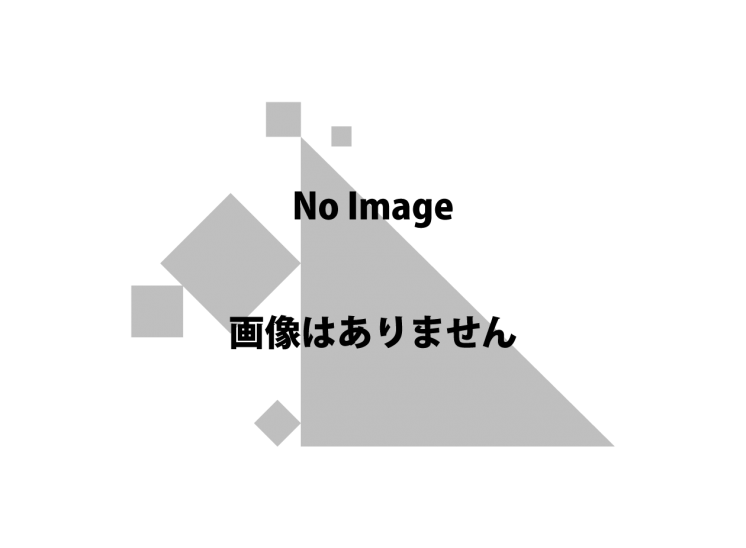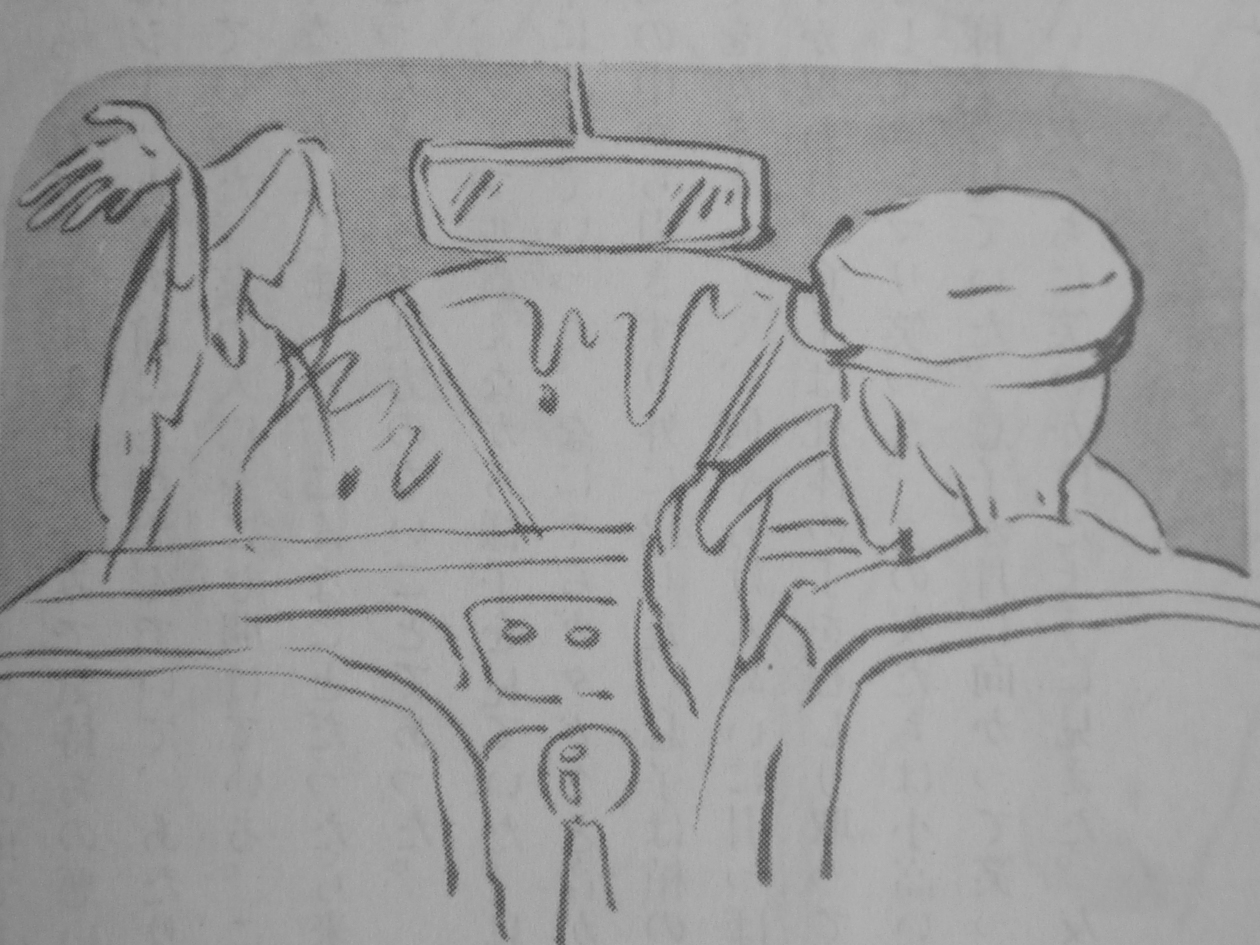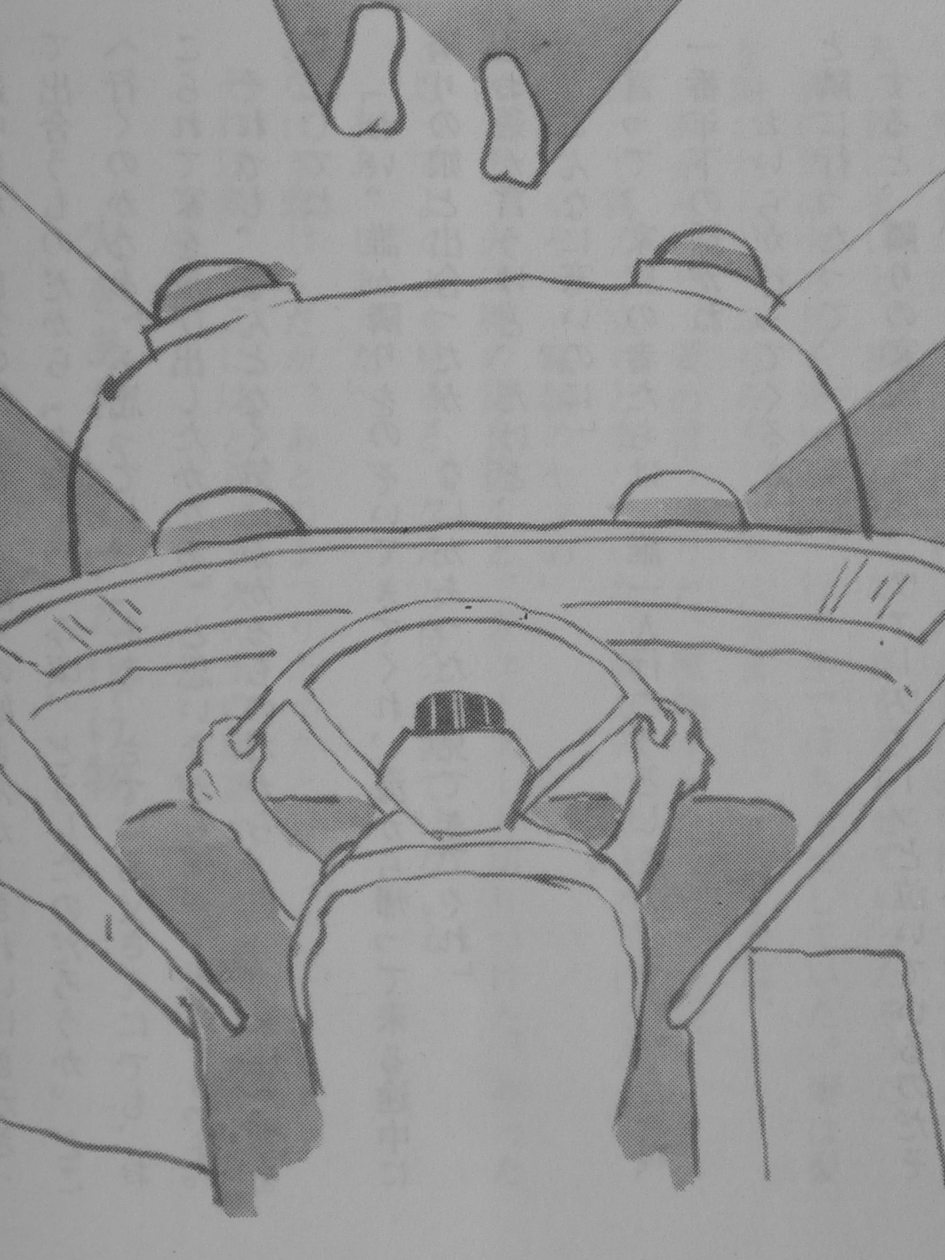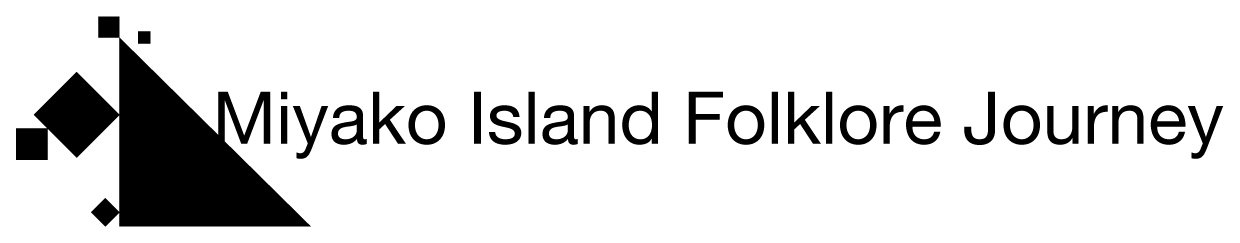『死体の始末』
昔、カウズガミといって、口の大きい瓶があったそうです。ある家のおかみが、その中に間男をかくまって、夫には分からないように時々食べ物を運んだりしていました。
夫は、ほんとうは気づいていたが、知らんふりをして様子を見ていました。しかし、だんだんと腹がたってきて、妻が留守のとき、湯をわかしグラグラ沸騰した湯を大口の瓶にぶち込んだので、男はあっけなく死んでしまいました。
夫は、男をどう始末しようか考えたが良い案が浮かばず、とりあえず俵に包み、家の隅の方へ放り投げて置きました。
そこへ、どろぼうが入り、隅にある俵を見つけ「これはいっぱい入っていそうだぞ」と、よいしょと持ち上げすたこらさっさ、逃げていきました。隠れて見ていた夫は、「やれやれ、こんなときはどろぼうも歓迎だ」と言ってにんまりしました。さて、どろぼうはその後、どうなったんでしょう。
(話者/佐渡山マツ=上野)